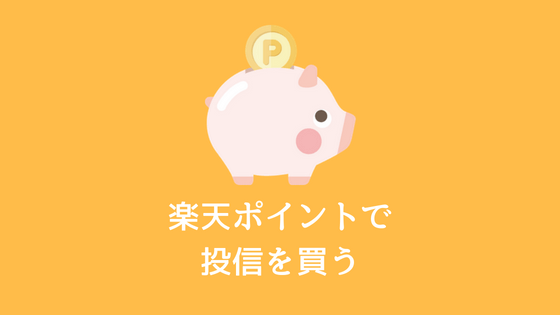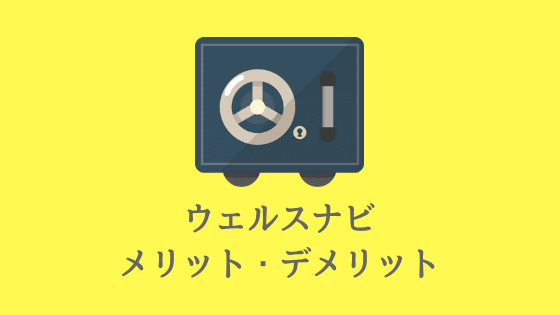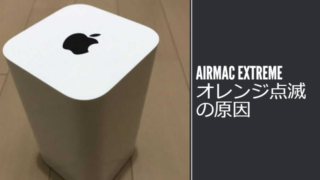つみたてNISA(ニーサ)とは、2018年1月1日から始まった投資の運用益が非課税制度です。
投資では売買を繰り返してしまうことや投資のよる税金で、個人投資家が儲からないと言われています。しかし、つみたてNISAは非課税で、一定の要件を満たすものしか扱っていないため、これから投資を始めようと考えている初心者におすすめな制度となっています。
「つみたてNISA」と「NISA」の違いやつみたてNISAのメリット、デメリットについて説明していきます。
スポンサーリンク
つみたてNISAとは
つみたてNISAは、投資によって運用益が非課税となる制度のことです。通常、投資によって得られた運用益には20.315%の税金がかかってきます。
例えば、投資したことで100万円の運用益があったとき約20万円が税金となるので、最終的な運用益は80万円となります。しかし、積立NISAを利用すれば、20万円の税金を支払う必要がなくなるのです。
つみたてNISAとNISAの違い
「つみたてNISA」と「NISA」は何が異なるのか知っていますか。「つみたてNISA」と「NISA」についてまとめてみました。
| つみたてNISA | NISA | |
| 対象者 | 開設年の1月1日現在で満20歳以上の日本人居住者 | |
| 非課税上限額 | 40万円 | 120万円 |
| 非課税期間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
| 投資可能期間 | 2018年1月〜2037年12月まで | 2023年まで |
| 非課税対象商品 | 積立・分散投資に適した一定の要件を 満たした公募株式投資信託、 ETF(上場投資信託)の分配金・譲渡益 | 上場REITや公募株式投資信託、 上場株式株式等の 分配金・配当金・譲渡益 |
| 口座開設可能数 | 一人1口座 | |
大きく異なる点は非課税上限額と投資可能期間です。「NISA」は非課税上限額が40万円であるのに対し、「NISA」は120万円となっています。
また、「NISA」の非課税期間は最長5年であるに対し、「つみたてNISA」は最長20年間と4倍になっています。少ないお金で長期間に資産形成した方は「つみたてNISA」が合っている制度でしょう。

つみたてNISAのメリット、デメリット
つみたてNISAのメリットとデメリットは以下の通りです。
つみたてNISAは20年間非課税の期間があるので、長期で運用することで複利によって資産形成できることが最大にメリットです。
複利とは、利子に対して利子がつくことを複利と呼びます。
例えば、100万円を年利5%で運用すると、1年後は105万円になります。2年後には105万円を年利5%で運用することになるので110.25万円となり、雪だるま式に利子が付いていきます。
非課税投資額は毎年40万円で月では33,000円になりますが、少ないと感じる方もいると思います。例えば、33,000円を5%のリターンで20年間運用したら1,300万円となるので、全然少ない額ではありません。
非課税投資額が毎年40万円であることはデメリットですが、一般的な家庭では十分な額です。
iDeCoの始め方
手順1:金融機関を決める
金融機関は以下の3つから選ぶのがおすすめです。
つみたてNISAはどこの金融機関でも非課税ということは変わらないのですが、店頭販売の金融機関では運用管理費用が高い商品しか扱っていないところもあります。
上記の3つの金融機関では、「eMAXIS Slimシリーズ」や「たわらノーロード」といった初心者にも商品を扱っています。金融機関を1度決めてしまったら、なかなか変えられるものでもないので、しっかりと考えて決めましょう。
手順2:資料請求する
金融機関を決めたらネットからつみたてNISAの申し込みをします。ネットから申し込むことですべての取引が完了するのではなく、まずは金融機関に資料請求します。
手順3:申し込み用紙に記入・提出する
金融機関から資料が届いたら、積立NISAの申し込み用紙を記入して提出します。
手順4:運用商品を決める
つみたてNISAの開設が完了したら運用商品を決めて積立します。つみたてNISAでは、非課税投資額が毎年40万円(33,000円/月)と決められているので、収まるように積立額を決めましょう。
さいごに
2018年につみたてNISAがスタートし、初心者が投資しやすい制度や環境が整ってきました。つみたてNISAの年間で40万円も積立できるので、つみたてNISAだけを利用しているだけでもよいでしょう。
つみたてNISA以外にもiDeCo(イデコ)と呼ばれる運用益の非課税や所得控除される制度もあります。投資に興味を持った方はつみたてNISAを始めてみることをおすすめします。

スポンサーリンク
スポンサーリンク